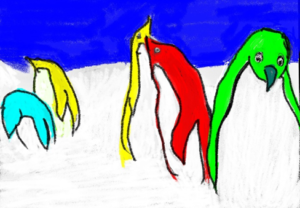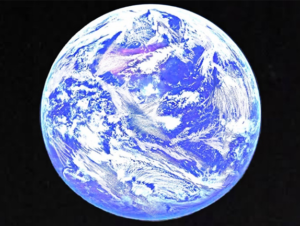最近、テレビで南極基地を紹介する番組やコマーシャルをよく見ますね。最新設備を備えた安全で快適な基地。移動する時は、最先端のハイテク雪上車やモバイルスキーなどいろんな移動手段があります。
1957年に、第1次越冬隊が南極に初めて上陸した時も、雪上車はありました。日本から運んできたのです。つまり移動手段はあったわけです。それなのに、なぜ、犬ゾリを引かせるために犬たちを極寒の南極まで連れて来たのでしょう。必要ないと思いませんか?
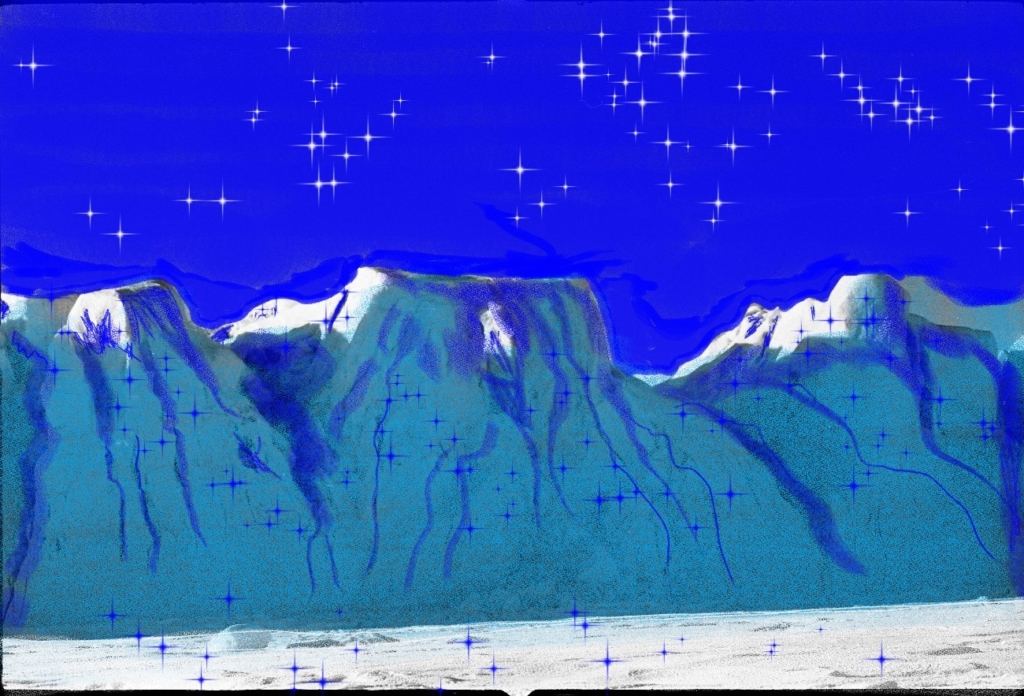
マイナス40度、風速50メートルの猛吹雪が吹き荒れる南極で、犬たちをソリにつなぎ、重い荷物を積んで走らせる。それは過酷な使役です。
「可哀そうすぎる」「動物虐待じゃないの」
そういう声があります。当然です。犬は人間の道具ではありません。
しかも、つらい事をさせた挙句、南極に置き去りにした。その結果、タロ、ジロ以外の、多くの犬たちは死んでいった。
この事実は許されることではありません。ただし、それは「現代の動物愛護の観点から見たら」という条件が付きます。
例えば環境問題。
産業革命が起きた18世紀半ばから19世紀、世界中の先進国が石炭をじゃんじゃん燃やし、大気を汚染し、地球環境を破壊し始めました。
「そんなことをしたら、地球の大気が汚染し、地球の温度が上がってしまうじゃないか」といった抗議運動など、もちろんありませんでした。
「21世紀の我々は地球環境を守ろうとしている。それに比べて、19世紀の連中は、地球環境のことなど考慮しなかった。なんてことをしてくれたんだ」と悲憤慷慨しても、意味はありませんよね。
「今の常識」で「過去の行為」を裁くのは、フェアではありません。
これは、科学技術の進化と、ライフスタイルの変化、という問題です。
昔は石炭を利用するしか、方法がなかった。現在は、いいか悪いかは別として原発もあるし、風力発電、太陽エネルギー発電があり、だからこそ、地球環境の改善に取り組めるのです。
つまり、最新の科学技術の恩恵を受けている現在に生きている私たちが、「現在の常識」や「現在の価値観」を振りかざして、過去の人々の行為を批判しても、意味がないわけです。
もし、そうした論法が許されるのなら、50年後、100年後の人々に、私たちは厳しく批判されるでしょう。
「どうして、行政が犬や猫を税金で殺したの?」「犬を虐待した人を、なぜ死刑にしなかったの?」「大気を汚染するガソリンエンジンの車を、どうして使い続けたの。バカじゃないの」「温暖化が進めば地球は滅ぶってわかっていたのに、どうして何もしなかったの」……
今の常識を持って、過去を裁くことの無意味さ、危険性を感じてもらえればと思います。
前置きが長くなりました。
今回から、「日本の越冬隊は、なぜ、犬たちを寒い南極に連れて来たのか?」という疑問を解明していきます。
今回は、その前に知っておくべき事実として、過去に起きた「2つの犬たちの悲劇」(真実の話)について、書こうと思います。
驚かれるかもしれませんが、第1次南極越冬隊の当初の実施計画では、カラフト犬たちを南極に連れていくというプランはなかったのです。犬たちは南極に行くはずではなかった。しかし、結局行くことになってしまった。なぜなのか――。
日本が南極観測に参加することが決まったのは1955年。しかし、ここから問題が噴出します。
いったい、どうやって南極に行くのか。
船か?その船はどこにある?
機材は何がいる。誰か知っている奴はいるのか?
そもそも、いったい誰が南極で1年間すごすことができるんだ?
そんな寒さに強い奴、日本にいるのか?
すべてはゼロからのスタートでした。
すべてを仕切るのは、「日本学術会議」という学問的な組織の中に作られた「南極特別委員会」でした。
まず、南極に向かう船。これは、「宗谷」というボロ船を改造して、なんとかすることになりました。
通信機材や、基地施設内の暖房装置、建物をプレハブで作る工法などは、民間企業の協力でなんとかなるめどが立ちました。
問題は、南極大陸での移動手段。南極観測をする以上、ずっと基地に閉じこもっていては研究になりません。何百キロも移動して調査研究する必要があります。歩いて行けるわけはないので、移動手段は重要な問題でした。
当然、当初は「雪上車を使えばいいでしょう」という意見でまとまりました。
しかし、それは甘い見通しだったのです。
確かに、欧米各国の南極基地には、雪上車をはじめ、ガソリンで動く先端の機動車がありました。しかし、実情を調べていくうちに、トラブルが相次いでいることが分かったのです。エンジンがかからなくなった。燃料が凍結した。クレバスに転落した。それぞれの国では大活躍する雪上車も、マイナス40度、50度にもなり、台風並みのブリザードが吹き荒れる南極では、故障ばかりしていたのです。
「マジか……」。青くなった委員会は、雪上車を北海道でテストしました。すると、故障ばかりです。マイナス20度の北海道でも使い物にならない雪上車を、マイナス50度になる南極に持って行って、役に立つのか?やばいんじゃないか?
皆、不安になりました。
想像してみてください。
南極基地を出発して、200キロ先で雪上車のエンジンが壊れた。乗組員は主に科学者ですが、車の修理工ではありません。だから修理できない。南極にJAFはありません。修理に来てくれる人はいないのです。じゃあどうするか。200キロを歩いて基地に戻るしかありません。しかし、そんなことは不可能です。死んでしまいます。
「そうなったら、基地から救援隊を送ればいいじゃないか」。確かにそうですね。
しかし当時は、位置を正確に特定するGPSのようなシステムもなければ、携帯電話もない。無線機はありましたが、基地から少し離れるとまったく聞こえず、使い物になりません。
つまり、いったん出発したら、どこにいるのか分からなくなるのです。
ということは、基地から何百キロも離れた地点で雪上車が動かなくなれば、乗っている隊員たちは全滅するしかないのです。救援隊は、彼らの位置が分からないのですから。
南極特別委員会のメンバーは、そうした現実を突きつけられ、頭を抱えました。
「困ったぞ」。解決策を見いだせず、頭を抱えるメンバーたち。そこに救世主が現れます。
のち、第1次南極越冬隊長になる、西堀栄三郎さんです。京都大学山岳部出身。民間企業でさまざまな発明をした科学者であり、技術者。
その彼が「雪上車は南極では役に立たない。しかし、別の手段がある」と主張したのです。
「別の手段って。どうすりゃいいんですか」とすがるような目の委員たちに、西堀さんは断言しました。
「犬です。犬ゾリに荷物を積み、人が乗って移動するんですよ」
委員たちは最初に目が点になり、次に笑い出しました。
「犬なんか、いったい何キロの荷物を運べるんですか?」「だいいち、南極の寒さに耐えられる犬なんて、日本にいないでしょう」
ところが、いたんです。北海道だけに生息していたカラフト犬。
彼らは北海道で暮らす人々の家で「使役犬」として飼われていました。使役犬、つまり、働く犬です。小さなリヤカーや荷車などにつながれ、収穫した食べ物や、まき、小物などを積んで、運んでいました。
その名の通り、カラフト犬の原産地は、北海道よりさらに北にあるカラフト地方です。零下数十度の寒さに耐えるだけでなく、太い脚、強い内臓を持ち、物を引っ張る力が強い。まさに、ソリを引くのにもってこいの犬種だったのです。
「おお、そういう犬がいるのか」「じゃあ、問題は解決だな」
いやいや。そんな簡単な話ではありません。
だって、カラフト犬は、いったいどこにいるのか、どうやって集めるのか。
すでに飼い主がいる場合、強引に国が奪うわけにはいかない。
仮に犬たちを集められたとして、どこで、どんな訓練をすればいいのか。
「犬ゾリなんて見たことないぞ」「そもそも、何を基準に犬を選ぶのか」「だれが、犬ゾリ訓練をやるんだよ?」
いやはや、まったくもって、何も決まっていません。
しかも、もうひとつの問題が浮上してきます。
ここで、ちょっと別の話になります。
皆さん、南極点(南緯90度ジャストの地点)をご存じでしょうか。一番近い海岸から測っても、南極大陸の奥地1,300キロ地点にあります。
1911年に、「人類初の南極点到達」という名誉をかけて、英国のロバート・スコット隊と、当時は小国だったノルウェーのロアール・アムンセン隊が一番乗りを争うという、世界中が注目したマッチレースがありました。
スコット隊は、当時最新の機動ソリと、たくさんの荷物を運べる馬で移動する作戦。
一方、アムンセン隊は、犬ゾリだけの編成で挑みました。
当時の新聞などの予想は、スコット隊の圧勝でした。なんといっても内燃機関の燃焼で動くソリはスピードがあり、馬力がある。馬は犬の何倍もの荷物を運べるから豊富な食料を積み込める。リッチな探検隊です。
ところが意外なことに、圧倒的速さで南極点に到達したのは、53頭の犬を使い、4台の犬ゾリで移動したアムンセン隊だったのです。
1911年10月20日に基地を出発し、12月14日に南極点に到達。そして、一人の犠牲者も出すことなく、基地に戻りました。
一方、スコット隊が南極点に到達したのは、年が変わった1912年1月17日。なんと34日も遅れる惨敗を喫したうえに、失望の中で帰路についた彼らは寒さと飢えで全滅したのです。
スコット隊の敗因は、強力な内燃機関でスピーディに動くはずだったソリが故障。仕方なく重たいソリを隊員たちが押しながら移動。これで大幅な遅れになり、しかも、途中で結局ソリは放棄。馬はカチンカチンに凍った南極の氷雪の上を滑りまくり、まったく役に立たず、結局、隊員たちは歩くしかなかった。完全な戦略ミスでした。
アムンセンは犬ゾリを採用したことで、「一番乗り」の栄誉を手に入れました。
しかし、その後、世界中が驚く、とんでもないことが発覚しました。
アムンセンは、ある意味、極端に合理的な男でした。
まず、ソリを引く犬が疲れると、殺して食料にしたことが分かったのです。
この事実だけでも、世界中が怒り、批判しました。
ただ、これは、犬の肉を食べる習慣がある国の食文化を批判するのとは異なります。そこは、いっしょくたにしないように気を付ける必要があります。
さらに驚愕の事実が発覚します。なんと、アムンセン隊は、疲れていない犬たちも「計画的に」殺して食べていたのです。意味が分からないでしょうね。つまり、こういうことです。
スタート当初は、食糧などが満載されているから犬ゾリは重たい。だから、たくさんの犬が必要になる。
しかし、南極点に向かって何日も何日も進めば、当然食事をとり、いろんなものを消費します。その分、犬ゾリに積んだ食糧や消耗品は徐々に減っていくので、だんだん軽くなっていく。
最初は53頭必要だった犬は、前進するにつれて、40頭でもソリを引ける。そのうち、30頭で十分、20頭いればOK、というふうになっていくわけです。
そうした状況で、もはやソリを引く必要がなくなった犬を一緒に連れていけば、その犬たちの食糧まで必要になる。
「それは無駄でしかない」とアムンセンは考えたのでしょうか。だから「不要」になった犬たちは殺して、自分たちの食料にする。あるいは、まだソリを引いている犬たちの食糧にする。この場合は共食いです。
この考えに立てば、ソリに積み込む食料の総量は確かに少なくて済む。軽量化を達成するわけです。役に立たなくなった物を捨てるように、役に立たなくなった犬は殺す。しかも食料にすれば一石二鳥――それも一つの考え方なのかもしれませんが、皆さんは納得しますか?
ともかく、「もう、この犬たちは用済みだな」というタイミングが来ると、犬たちは次々に殺され、アムンセンたちの胃袋におさまったのです。基地に帰り着いたとき、殺されずに済んだ犬はわずか11頭だったそうです。
私は、このことを知った時、心底震えました。こういう発想をする人間が、この世にいることが信じられませんでした。「なんてことをしたんだ」という怒りを通り越した、恐怖でした。
「探検とは、そういうもんだ。甘いことを言ってるんじゃないよ」という人もいるでしょう。「とても合理的な計画じゃないか」と称賛する人もいるかもしれません。
人の意見はさまざまですが、少なくとも私は、とても同意できません。
「今の常識に照らして」ではなく「当時の常識に照らして」も許されないと思いますし、だからこそ、ノルウェー国内でも批判が起きたのでしょう。皆さんはどうですか?
「まあ、そういう極端に合理的な考えをする外国人はいるかもなあ」と思っているあなた。甘いですよ。実は、同じようなこと、いや、もっとひどいことをした日本人がいたのです。
個人攻撃はコラムの目的ではありませんから、実名は書きません。ただ、事実はしってほしい。
この日本人をA氏とします。ある年、彼は「南極上陸」を目指して日本を出港。その船には26頭のカラフト犬を乗せていました。カラフト犬は寒さに強いので、選ばれたのでしょう。
しかし、寒さに強いということは、逆に言えば暑さには弱いわけです。日本から南極に行くには、必ず猛暑の熱帯地域を通過します。暑さに弱いカラフト犬たちはどんどん弱っていきました。24頭が死にました。しかしA氏は日本に引き返そうとしませんでした。
残るは2頭。名前を太郎と次郎といいました。そう、第1次越冬隊が連れていき、置き去りにし、それでも生き抜いた2頭のカラフト犬、タロ、ジロは、この強運を持った太郎と次郎にちなんで付けられた名前だったのです。
しかし、そのうちの次郎も食欲がなくなり、足がもつれるようになり、最後は泡を吹いて死んでしまいました。最後まで生き抜いたのは、太郎、ただ一頭だけだったのです。
南極に上陸できたとしても、太郎だけでは犬ゾリは引けません。こうしてA氏の無謀とも思える南極計画は、25頭の犬たちを無駄死にさせて終わったのでした。
暑さだけでなく、衛生管理や犬の健康管理が悪く、犬たちは内臓をやられたという説もあります。
いずれにしても、これだけの犠牲を出せば、反省して南極上陸はあきらめると思うのですが、A氏はあきらめませんでした。
再び犬を集め、生き残った太郎と、新たに手に入れた29頭の合計30頭で、もう一度南極探検に向かったのです。
1912年1月20日、南極大陸の沿岸に上陸。犬たちは体調が悪く、下痢ばかりしていました。血を吐く犬もいて、4頭が死亡しました。残りは26頭。
2月3日、探検隊は帰国することに。Aさんを先頭に、隊員が乗船。次いで、犬たちも船に乗り込み始めましたが、A氏が船に乗せたのは5頭だけで、突然出航命令を出しました。
戸惑う船員たち。南極大陸の沿岸には、まだ21頭のカラフト犬が船に乗せてもらうのを待っています。しかしA氏は、カラフト犬21頭を南極に置き去りにしたのです。
自分たちも船に乗せてもらえると思っていたカラフト犬たちは、どんな気持ちだったでしょう。
「おーい、ぼくたちは、まだここにいるよー」
そう言わんばかりに、いっしょうけんめい吠え、大きくしっぽを振り、遠ざかる船を追いかけて、海岸の氷雪をずっと走り続けたそうです。

その姿を見て「Aさん、犬たちのところに戻ってください」「犬たちを船に乗せてあげてください」と船員たちは頼んだのですが、Aさんは聞き入れませんでした。
船は南極大陸からどんどん遠ざかり、もはや犬たちの姿は豆粒のようになりました。犬たちの悲痛な鳴き声も聞こえないはずなのに、船員たちは、なぜか犬たちの悲鳴が聞こえたように思ったそうです。
一生けん命走り、人間に尽くし、挙句の果てに、突然南極に置き去りにされた犬たち。
どれほどの絶望を感じているのか――。そう思うと、船員たちは涙が止まりませんでした。
A氏は、帰国後、犬たちを見殺しにしたことを公表しませんでした。事実を伏せたまま、各地で「南極探検講演会」を開き、多額の金を手に入れました。
実は、第一次南極越冬隊長の西堀栄三郎さんは、子供のころ、京都でA氏の講演を聞いて「自分も南極に行きたい」と心躍らせたそうです。犬を南極に置き去りにした人物だと知る由もなく、「彼は英雄だ」と思っていたのです。
そして数十年後、自分も犬を南極に置き去りにしてしまった。なんという運命の皮肉でしょう。
のちに犬を置き去りにした事実がばれたA氏は、「南極の英雄」から一転して「人でなし」と日本中から批判されるようになりました。
なぜ犬たちを見捨てたのか。
A氏の釈明が本当かどうか、確かめようがありませんが、「船に飲み水が少なかった。犬の分までは、なかった」というのが理由でした。
飲み水が少なくなったのであれば、南極には雪が固まった雪塊や氷がたくさんあるのですから、探検している間に、船員たちに雪塊を船に運ばせて、水桶に保管しておけば問題ありません。
そんな簡単なことができないわけがないというので、この釈明は人々を納得させることはできなかったようです。
こうして、当初はA氏を支持していた人たちも次々に離れていきました。犬たちを見殺しにしたことが発覚してからは、寂しい晩年だったようです。
話は本題に戻ります。
第1次南極越冬に、カラフト犬を採用することは決まった。しかし、どうやって犬を集めるのかといった多くの問題とともに、別の問題も浮上してきた、と書きました。
別の問題とは、反対運動です。「犬を南極に連れていくな」という運動です。
当時の日本人の間には、南極に犬を置き去りにして見殺しにしたA氏の残虐な行為が強い衝撃として残っており、「また南極に犬を連れていくのか」「そして、また置き去りにするんだろう」という不安が生まれたのです。
そして、全国の愛犬家たちを中心に「カラフト犬を再び南極に連れていくな」という反対運動が巻き起こったのです。
何も決まらない中で、南極に行くことだけが決まっている。
問題解決の糸口は見えないまま、反対運動は激化していきます。
南極観測の成功のカギを握るカラフト犬たちの問題は、これからどうなっていくのでしょう。
次回は、カラフト犬の飼い主の所在地調査、犬たちの選別、訓練の実態と、反対運動の広がりついてご紹介します。
(written by Free Dog)
(不定期掲載)
【ミニ解説】 日本の南極第1次越冬隊は多くの犬を南極に連れて行った。しかし1年後、2次越冬隊との交代に失敗。結局15頭を鎖につないだまま南極に置き去りにした。全滅したと思われていたが、1年後、なぜかタロとジロの2頭は生きていた。世界中が驚き、「タロジロの奇跡」と言われている。
★このブログを書くにあたり、小学館集英社プロダクションの許諾を得ています。
★興味ある方は、こちらをご覧ください